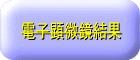|
 |
|
||||
| [理想化学式] (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6 銅,亜鉛の炭酸塩鉱物である。色は水色のものが結構多いが,薄い緑色,白っぽい水色,くすんだ水色のものなどもある。水亜鉛土とは理想科学式の一部が銅に置き換わったくらいの違いであるが別鉱物として分類されている。一般的には結晶は針状または羽毛状あるいは鱗片状のものが多く単斜晶系であり,絹糸光沢または真珠光沢を放つ。硬度は1〜2と非常に柔らかく,勢いの強い水道水などでの洗浄またはブラッシングで容易に結晶が壊れていったり変形していくため洗浄や取扱などには非常に注意を要する。塩酸に対しては孔雀石と同様容易く発泡しながら溶けていく。しばしば孔雀石,菱亜鉛鉱,水亜鉛土,異極鉱などの銅や亜鉛の二次鉱物と共生することがある。この鉱物に含まれる亜鉛と銅のラテン語が名前の由来だそうだ。日本でも新潟県の三川鉱山,静岡県の河津鉱山,滋賀県の湖南市(一般的には石部町灰山と呼ばれている)などいくつか有名な産地がある。中国地方でも岡山県の小泉鉱山,広島県の平子鉱山など所々で見られやはり銅と亜鉛の二次鉱物が見られる鉱山ではしばしば目にすることがある。この鉱山ではズリの表面や晶洞中に立体的あるいは平面的に板状結晶,針状結晶を成したものが時々見られる。拡大写真のものは母岩を割った際に出てきたものであるため汚れが少なく微細な放射状結晶が集合しており絹糸光沢を放っている。 MENUページに戻る 前のページに戻る |
||||||