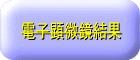|
 |
|
||||
| [理想化学式] PbSO4 鉛の硫酸塩鉱物である。色は透明,白色,黄色,薄緑色,ピンク色のものなど多彩な色を示すことがあるが一般的には白色,黄色のものが多い。直方晶系である。結晶は透明または半透明で先端が屋根のように尖ったものが多い。他には八面体の結晶のように見えるものやコロッとしたような結晶を示すことがある。ただ方鉛鉱などの鉛鉱物の表面が変化して被膜状または塊状に変化したようなものがほとんどである。硬度は2.5〜3,比重は6.4とされている。鉛を主成分としているので結晶の大きなものは重量感を感じることができる。日本名は鉛の硫酸塩鉱物が名前の由来であるが,一方英名は模式標本地のイギリスのウェールズ北西岸に接するアングルシー島が名前の由来となっている。海外ではイタリア,モロッコ,アメリカ,オーストラリアなど世界の所々で見られるが,モロッコ産のものは美しいものが多い。日本では秋田県の亀山盛鉱山,新潟県の三川鉱山,岐阜県の神岡鉱山など各地で見られる。二次鉱物が生成しやすい環境で鉛を多産する鉱山では皮膜状のものが見られる場合が多いが,皮膜状であることから見逃される場合も多い。銅珍鉱山では方鉛鉱,閃亜鉛鉱,硫カドミウム鉱などとともに見られる。拡大写真では空隙に生成されているため分かりずらいが,石英の上方にくすんだ白色の粒状のものが本鉱である。ただ皮膜状のものなどほとんど見られないため量自体は少ないのではないかと思われる。顕微鏡写真では練乳色をした八面体の結晶が確認できる。一部負晶となっている部分がある。銅珍鉱山ではモリブデン鉛鉱も産出していることから,当初パウエル石を疑ったが電子顕微鏡での分析により鉛と硫黄を検出し硫酸鉛鉱と同定した。ちなみにパウエル石も八面体様の結晶を示す場合があるが,硫酸鉛鉱に比べるとシャープな感じを受ける。 MENUページに戻る 前のページに戻る |
||||||