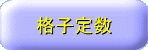|
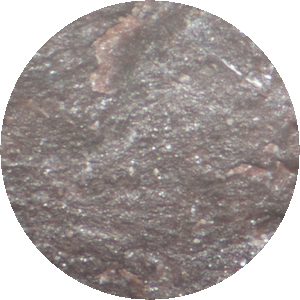 |
|
|||||
| [理想化学式] Mn5(SiO4)2(OH)2 マンガンの珪酸塩鉱物である。珪酸塩鉱物の中ではネソ珪酸塩鉱物に分類される。色はピンク色,赤褐色,淡灰褐色のものが多く,ガラス光沢または亜ガラス光沢を示す。結晶ははっきりしたものを目にすることはほとんどなく,塊状のものが多い。単斜晶系である。アレガニー石とは同質異像の関係になる。ヒューム石グループのリューコスフェニ石サブグループに属する。硬度は5,比重は3.9とされている。接触変成層状マンガン鉱床中,広域変成層状マンガン鉱床から産出し,菱マンガン鉱,ハウスマン鉱,アレガニー石などと共生する。逆にバラ輝石,満礬ザクロ石,石英など珪酸分の富んだ鉱物とは共生しないとされている。アメリカの鉱物学者のドナルド・ラルフ・ピーカー氏らにより,同じくアメリカの鉱物学者であるポール・ヒューバート・リッベ氏に敬意を表して名付けられた。ナミビアのオチョソンデュパ州オタビ県にあるコンバット鉱山のものが模式標本とされている。海外ではナミビア,ロシア,ルーマニアなどで産出が確認されているが,産地は少ない。日本では栃木県の加蘇鉱山,愛知県の足山鉱山,京都府の向山栗谷鉱山など所々で産出が確認されている。阿品鉱山ではズリ中にテフロ石を伴い,暗い褐色で塊状を成してわずかながら産出する。拡大写真では全体的に見られる暗い褐色が本鉱である。顕微鏡写真でも結晶は見られなかった。当初は満礬ザクロ石,アレガニー石などの他のマンガン鉱物と考えたが,X線回折分析を行ったところ,一部にテフロ石や不純物のピークが見られたものの全体的にリッベ石にかなり近いピークを示していることが判明した。格子定数を計算してみたところa=4.805,b=10.764,c=15.717,V=812.80Å3となった。模式標本地の格子定数と近い値をとっている。 MENUページに戻る 前のページに戻る |
|||||||