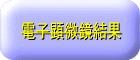|
 |
|
||||
| [理想化学式] Cu5(AsO4)2(OH)4 銅の砒酸塩鉱物である。色は暗い鮮やかな緑色のものや深緑色のものが多い。樹脂光沢を示す。半透明〜不透明で房状または皮膜状のものが多い。単斜晶系である。母岩の表面や割れ目に生成される場合が多い。結晶が微細であるため硬度や比重を測ることは難しいが,硬度は4.5で比重は4.2とされている。砒素と燐が置換したものは擬孔雀石となる。コーンウォール石と擬孔雀石では色の違いはあまり当てにならないが、コーンウォール石の方が緑が鮮やかまたは濃く,擬孔雀石の方が青っぽい緑色をしているように思われる。砒素を含む鉱床に二次的にできる場合が多い。イギリスのコーンウォールで発見されたことが名前の由来だそうで,チェコの鉱物学者であるフランツ・クサーヴァー・ツィッペ氏により名付けられた。海外ではアメリカ,イギリス,フランス,オーストラリアなど各国で見られる。日本では奈良県の三盛鉱山,栃木県の日光鉱山などで少量見られたが,鉱山以外では広島県の瀬戸田が有名な産地である。山上鉱山ではズリに砒酸塩鉱物を産する部分があり深緑色の房状を成し,斜開銅鉱などとともに見られる。他には孔雀石,ブロシャン銅鉱,擬孔雀石,珪孔雀石などの銅鉱物も見られる。このうち孔雀石,ブロシャン銅鉱は針状,柱状を成しているものが多く判別は可能である。珪孔雀石も房状を成しているものがあり,珪孔雀石は破断面が縞状になっており,これが確認できれば判別し易い。擬孔雀石についても房状,皮膜状を成しているが,コーンウォール石の方は深緑色が強く,擬孔雀石は青味の強い緑色のものが多いように思う。EDS分析の結果は掲載していないが,銅,砒素,燐が検出された。砒素>燐となっており房状の結晶形態からコーンウォール石と同定している。 MENUページに戻る 前のページに戻る |
||||||