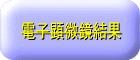|
 |
|
||||
| [理想化学式] BiCu6(AsO4)3(OH)6・3H2O 銅とビスマスの砒酸塩鉱物である。色は明るい緑色または水色であるが,緑色のものは通常の緑色といった色ではない。ややくすんでいたり淡いものが多い。一般的に結晶は針状,柱状結晶が放射状に集合しているものが多い。羽毛状の結晶が集合しているものもある。ミクサ石やアガード石はミクサ石グループを構成しているが,ミクサ石グループはこうした結晶をなしているか皮膜状のものがほとんどである。六方晶系である。硬度は3〜4,比重は3.8とされている。チェコの鉱山技師のアントン・ミクサ氏に敬意を表したオーストリアの鉱物学者のアルブレヒト・シュラウフ氏により名付けられたそうだ。海外ではイギリス,ドイツ,ギリシャ,アメリカなどで産出する。日本での産地は今のところ大和鉱山の他,栃木県の日光鉱山,岐阜県の一柳鉱山のみで産出が確認されており希な鉱物である。大和鉱山のミクサ石はズリ中の石英の表面に産出するものが多く,付近にホセ鉱Aなどの含ビスマス鉱物が見られる場合がある。このミクサ石が産出するズリには針状の孔雀石やザレシ石も産出する。ザレシ石は草緑色もしているものが多く区別しやすい。孔雀石の似た感じのものは同定が難しい場合があるが,孔雀石とも若干の色調の違いで見分けられることが多い。日本地学研究会監修の「地学研究」vol.62No.2に産出についての記載があり,当時は皮膜状のもののみであると記載されているが結晶を成しているものも見られる。拡大写真では全体に点在している明るい青緑色をした鉱物が本鉱で,柱状結晶が集合している。SEM像ではその様子がよく確認できる。EDSにより分析を行い,ビスマスが検出されたこととビスマス>カルシウム>鉛となっていることビスマス+カルシウム+鉛と銅と砒素の構成元素比率(At%)がだいたい1:6:3に近いことからミクサ石と同定した。 MENUページに戻る 前のページに戻る |
||||||