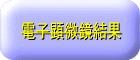|
 |
|
||||
| [理想化学式] Mg2Si2O6 マグネシウムの珪酸塩鉱物である。色は薄茶色,麦わら色のものが通常だが,白色,赤色に近いもの,黄色,オリーブ色,茶色など色々な色のものがある。半透明または不透明である。ガラス光沢または真珠光沢を示す。斜方晶系である。結晶は日本では針状または柱状のものが集合して放射状になったものが見られる。海外では薄板状の単結晶のものも見られる。マグネシウムを鉄に置換したものは鉄珪輝石となる。マグネシウムと鉄は化学組成上連続し中間のものも存在する。以前は連続しているものを古銅輝石や紫蘇輝石などと呼んでいたが現在は使われることはなくなった。一般的に硬度は5〜6で比重は3.2〜3.9とされている。ギリシア語の火に耐えるから名付けられたそうだ。フランス,ドイツ,スペイン,アメリカなど世界の色々な所で見られる。日本の産地は鉱山では岩手県の釜石鉱山,鳥取県の若松鉱山,岡山県の高瀬鉱山などで産出した記録が残っている。西日本ではあちらこちらのクロム鉱山で見られたようだ。鉱山以外では岩手県宮古市川井の麦わら色の菊の花が咲いたような放射状のものが有名であり,通称「菊寿石」と呼ばれていて見栄えが良い。蛇紋岩帯に見られることが多い。広瀬鉱山の頑火輝石はズリ中に柱状または板状結晶が集合しているものが所々見られ比較的見つけやすい。拡大写真では所々に見られる麦わら色の部分が本鉱である。顕微鏡写真では柱状結晶が集合しているのが観察される。EDS分析の結果はマグネシウム+鉄と珪素の比率がだいたい1:1になっている。マグネシウムの端成分となっておらず10%前後の鉄を含んでいる。X線回折分析では鉄珪輝石とわずかなズレがあり,頑火輝石のピークとほぼ一致した。以上のことから頑火輝石と同定している。 MENUページに戻る 前のページに戻る |
||||||