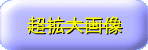|
 |
|
|||||
| [理想化学式] (Cu,Zn)2(CO3)(OH)2 銅,亜鉛の炭酸塩鉱物である。色は緑色〜群青色の範囲で色々な色彩を成す。青緑色のものやくすんだ薄い青色のものが多い。銅と亜鉛がだいたい一定の範囲内で変化するようで,その割合によって微妙に色彩が変化するようである。ガラス光沢や絹糸光沢を示す。日本名では亜鉛孔雀石とも呼ばれている。孔雀石とは理想科学式の一部が亜鉛に置き換わったくらいの違いであるが別鉱物として分類されている。孔雀石などとともにローザ石グループを形成している。単斜晶系である。一般的には結晶は針状が集合して丸くなり毛羽立ったようなものが多く,個人的には,色は異なるが植物のアザミの花に似ているような感じがする。他にも球状あるいは放射状になっているものがある。硬度は4.5と孔雀石よりは硬く,他の二次鉱物と比べるとやや硬い感じ がする。比重は4.0〜4.2とされている。塩酸に対しては孔雀石と同様発泡しながら溶けていく。孔雀石,水亜鉛銅鉱,菱亜鉛鉱,白鉛鉱,水亜鉛土などと共生することが多い。銅鉱床でも亜鉛に富んだ鉱床で見られるような感じを受ける。イタリアのサルディーニャ州南サルディーニャ県ナルカオのローザ鉱山のものが模式標本となっており,名前の由来にもなっている。ドイツ,ポルトガル,ナミビア,メキシコを初めとして世界各国で見られる。日本では新潟県の三川鉱山や静岡県の河津鉱山などいくつか産地がある。大倉鉱山ではズリ中の方解石の表面あるいは近くに希に見られる。色は薄いくすんだ青緑色で房状に生成しているものが見られた。拡大写真では左上の端に近い部分に結晶が多く見られる。方解石上のその他の薄いすんだ青緑色のものは皮膜状になっているがやはり本鉱であると思われる。EDS分析した結果,一定量の亜鉛が含まれていた。 MENUページに戻る 前のページに戻る |
|||||||