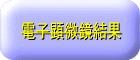|
 |
|
||||
| [理想化学式] NaFe3(SO4)2(OH)6 ナトリウムと鉄の硫酸塩鉱物である。鉄明礬石のカリウムがナトリウムに置き換わったもので.明礬石グループの一員である。明礬石のスーパーグループの中の明礬石グループ,ビューダン石グループ,鉛ゴム石グループの鉱物にも類似したものがある。鉄明礬石,ビーバー石−Cu,亜鉛ビーバー石,鉛ゴム石,ビューダン石,ヒダルゴ石などとよく似ており肉眼での同定は難しい。海外では結晶のものも産出しているようだが,結晶自体微小なものが多く,ほとんどのものは粒状,房状,皮膜状あるいは塊状である。色は黄色,オレンジ色,茶色のものがほとんどで結晶のものはガラス光沢,塊状のものは土状光沢を示す。三方晶系である。硬度は2.5〜3.5で比重は3.2とされている。鉄明礬石のカリウムがナトリウムに置き換わったものが名前の由来になっている。海外ではドイツ,オーストリア,ギリシア,アメリカなど各国で見られる。日本では京都府京都市,和歌山県那智勝浦町で産出が確認されている。見た目が被膜状あるいは土状なので,見逃されていることも考えられる。先の産地のうち和歌山県那智勝浦町も海岸の鉱床であり,海岸に沿った鉱床で注意深く観察すればまだまだ新たな産地が増える可能性がある。志津木鉱山では,ズリの一部で多く見られる部分がある。色はあまり当てにならないが.鉄明礬石より黄色味が強いように感じられる。成因は鉄明礬石が生成される際に海水中のナトリウムが反応して生成されたと考えられるが,正確には不明である。拡大写真では母岩に皮膜状に生成されている黄土色の部分が本鉱である。顕微鏡写真でも結晶は確認できず,皮膜状に見えている。 MENUページに戻る 前のページに戻る |
||||||