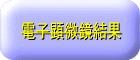|
 |
|
||||
| [理想化学式] Sb2O3 アンチモンの酸化鉱物である。色は無色透明〜白色であるが中には黄色,オレンジ色を示すものも見られる。絹糸光沢またはガラス光沢を示す。斜方晶系である。結晶は針状または板状,柱状のものが密集し放射状になっているものが多く見られる。他には微結晶が集合して粒状,球状になったものが見られることがある。国内でもルーペ,顕微鏡大で結晶が確認できるものが見られることがある。方安鉱とは同質異像の関係にある。また方安鉱と共生することもある。硬度は2.5〜3,比重は5.8とされている。アンチモン鉱床の酸化帯に産出する場合が多いが必ず見られるといったほどではなく所々で見られる程度である。15世紀のドイツのバシリウス・バレンティン氏が名前の由来だそうだ。海外ではアルジェリア,ギリシャ,イタリア,チェコなど世界各国で見られる。日本では愛媛県の市ノ川鉱山,宮崎県の鹿川鉱山などで見られる。他にも島根県の富田鉱山,広島県の正和鉱山でも産出を確認している。高城鉱山のバレンチン石はズリ石の表面や割った石の割れ面に付いていることが多い。ただ表面のものは褐鉄鉱による汚染がひどく分かりづらい。輝安鉱,ベルチェ鉱とともに比較的見られる。拡大写真はズリ石を割ったもので石英質の母岩の表面のあちらこちらに見られるくすんだ黄色の部分が本鉱である。顕微鏡写真では針状結晶が不規則に集合しているのが確認できる。この標本はルーペでも十分結晶が確認できるものだが,現地でもこうした結晶がルーペで十分確認できるものも見られる。以前,肉眼鑑定により黄安華と同定していたが,結晶形態からセルバンテス石の可能性も考えられたことから正式にX線回折分析を行ったところ意外にもバレンチン石のピークと一致した。 MENUページに戻る 前のページに戻る |
||||||