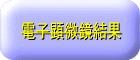|
 |
|
||||
| [理想化学式] Bi2MoO6 ビスマスのモリブデン酸塩鉱物である。色は一般的には薄黄色,白〜灰色であり絹糸光沢を示す。一般的には皮膜状または土状を成しているが,外国産のものには針状結晶を成すものも見られる。直方晶系(斜方晶系)である。硬度を記載している文献は見当たらないが,比重は計算上8.3とされかなり大きい。オーストリアの鉱物学者でウィーン自然史博物館の学芸員であるルドルフ・イグナッツ・ケクラン氏が名前の由来だそうだ。海外ではドイツ,チェコ,アメリカ,オーストラリアなど数か国で産出が確認されているが,産地はあまり多くない。「日本産鉱物型録」という文献によれば日本では岐阜県の恵比寿鉱山で産出したという記録があるくらいで余り多くないが,岡山県の加茂鉱山,広島県の瀬戸田鉱山,同じく広島県の市ノ畑鉱山でも産出を確認した。ビスマスとモリブデンはどちらも高温熱水鉱床または気成鉱床に見られることが多く,山陽地方の他のモリブデンを産出する鉱山のほとんどはこれらの鉱床であるため他にも産出する可能性がある。モリブデン酸塩がタングステン酸塩に置き換わるとラッセル石になる。ビスマス,タングステン,モリブデンの二次鉱物は発色性の強い銅などを含むものは別にして,おおよそ黄色であるため見分けがつきにくい。特にこの鉱山で産出するベトパクダル石−CaCaとは非常に区別がつきにくい。南生口鉱山ではズリ中の石英の表面に,輝水鉛鉱を伴い希に見られる。モリブデンは輝水鉛鉱が分解したものと思われ,ビスマスは泡蒼鉛などの二次鉱物または顕微鏡以下の大きさの自然蒼鉛などの金属鉱物の分解により生成したものと思われる。拡大写真では右下隅の狭い範囲のくすんだ薄黄色部分が本鉱である。顕微鏡写真では土状または皮膜状の黄色の部分が本鉱である。EDS分析ではモリブデン,ビスマスがほぼ2:1で検出されたためケヒリン石と同定した。 MENUページに戻る 前のページに戻る |
||||||