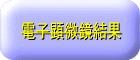|
 |
|
||||
| [理想化学式] (Na,Ca)1−X(Mn,Mg)6O12・3−4H2O マンガンの酸化鉱物で,A1−XB6O12・3−4H2OとするとAサイトにはナトリウム,カルシウム,カリウム,バリウム,マグネシウム,Bサイトにはマンガン,マグネシウム,アルミニウムなどが入る。結晶では黒色または暗灰鋼色で金属光沢を示し,塊状では黒色の土状光沢を示すことが多い。結晶は針状や房状の集合したものが多い。単斜晶系である。硬度は1.5で比重は3.7とされている。かなり柔らかい鉱物で爪で引っ掻くと筋が残る。マンガン鉱床の二酸化マンガン鉱が多く生成された鉱床などで見られる。パイロルース鉱,水マンガン鉱,菱マンガン鉱などと共生することがある。北海道余市町の轟鉱山から発見されたのが名前の由来だそうだ。日本で発見され、独立種として承認された最初の鉱物である。世界でも各国で発見されている。日本でも各地に産出し,有名なものは北海道の轟鉱山,静岡県の池代鉱山などである。池代鉱山は立入禁止となっているがかつては消し炭状のものを産出した。中国地方でも島根県の豊稼鉱山,山口県の小藤鉱山,山口県萩市の瓜作などでも見つかっている。岡山県の名草鉱山では近くにある林道の露頭に見られる。扇状のものの他消し炭状,樹枝状のものも見られる。拡大写真では黒い部分が本鉱である。顕微鏡写真やルーペでは針状結晶が扇のように集合しているものが観察できる。XRD分析(X線回折分析)を行ったところ,一部に石英の混入が見られるものの轟石のピークとほぼ一致している。EDS分析でもほぼ轟石と一致した結果が得られた。 MENUページに戻る 前のページに戻る |
||||||