 |
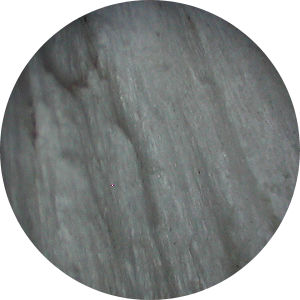 |
|
|||||
| [理想化学式] Ca6Si6O17(OH)2 カルシウムの珪酸塩鉱物である。一般的に不純物として鉄やマンガンを含む場合がある。色は通常,無色透明〜白色半透明であるが,鉄やマンガンを含む場合は薄いピンク色や薄茶色になる場合がある。ガラス光沢,絹糸光沢,真珠光沢を示す。放射状,針状若しくは毛状の結晶を成して産する。房状のものも見られるが,詳しく観察すると放射状結晶の集合体であることが多い。単斜晶系である。硬度は6.5で比重は2.7とされている。ドイツの鉱物学者のカール・フリードリヒ・オーガスト・ランメルスベルグ氏により,発見地であるメキシコのプエブラ州のテトラ・デ・ゾノトラに因んで名付けられた。イタリア,南アフリカ,アメリカ,オーストラリアなど世界各国で見られるが,今のところ中国,フランス,南アフリカを除くアフリカ諸国,南アメリカ大陸での産出は確認されていない。日本では鉱山では岩手県の釜石鉱山,鉱山以外では三重県の白木,岡山県の布賀,広島県の久代など所々,産出報告がある。石灰岩,蛇紋岩,斑レイ岩中の変成鉱床や高温スカルン鉱床などに見られる。トバモリー石や珪灰石と共生していることが多い。三原鉱山ではゲーレン石や加水ザクロ石などの高温スカルン鉱物を産するズリ中に見られる。拡大写真では向かって左半分の白色の部分が本鉱である。白色部分の下部には放射状結晶がはっきり認められるが,その他の部分もじっくり観察すると全体的に放射状結晶が積み重なっているのが確認できる。一見珪灰石とよく似ており,このズリには珪灰石も多く見られるため珪灰石かと考えたが,このズリで見られる珪灰石とかなり異なっていることと白色味が強かったため念のためX線回折分析を行った。その結果,ゾノトラ石のピークと一致していたことからゾノトラ石と同定した。顕微鏡写真は下部の放射状結晶を撮影したものだが,さらに細かい絹糸光沢を成す白色筋状結晶の集合体であることが確認できる。 MENUページに戻る 前のページに戻る |
|||||||




